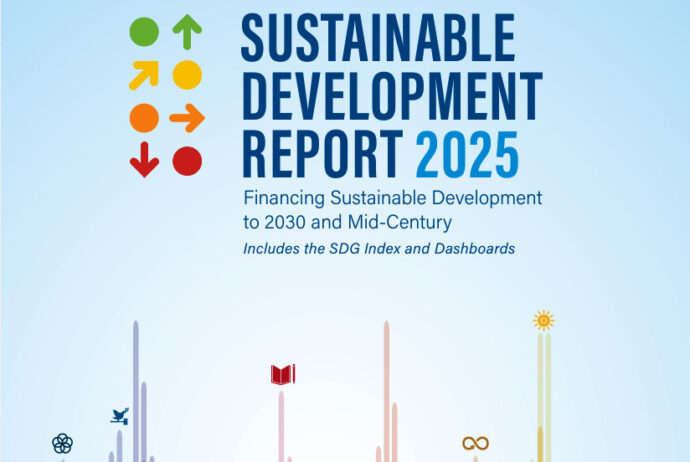2030年まで残り5年となりました。最新の国連報告の内容は、先のブログでも触れました。(SDGs進捗の年次報告2025/気象変動への対応が遅れる)
SDGsは世界的に達成軌道から遅れており、紛争や財政余力の不足、気候危機の進行が大きな要因とされています。日本は総合19位と上位ですが、気候変動、生物多様性、資源循環、ジェンダー平等の分野で改善の余地が残ります。
こうした状況を踏まえ、茨城県としては次の「四つの柱」を同時並行で進めることが重要だと考えます。

第一の柱は、脱炭素と産業競争力の両立です。沿岸域の再生可能エネルギー導入や、蓄電・水素・パワーエレクトロニクスといった産業基盤は県の強みです。港湾・工業地帯を核に、系統強化、需要家側の省エネ・電化、再エネの面的導入を計画的に進め、地域のGX(グリーントランスフォーメーション)を加速します。その際、設計・施工・運用・保守の各段階で女性を含む多様な人材が参画できるよう、資格取得支援や託児を伴う技能講座、現場配置の見直しを進め、人材不足の解消とイノベーションの創出を両立させます。
第二の柱は、強靱化の質の向上です。地震・津波など複合災害リスクに備え、避難計画の実効性検証、避難路・高台・垂直避難施設の維持更新、インフラ点検のデジタル化を着実に進めます。さらに、学校・病院・庁舎・港湾施設のマイクログリッド化によって、平時の省エネと非常時の電力・通信確保を両立します。避難所運営にはジェンダー配慮を組み込み、プライバシー確保、月経関連物資や乳幼児対応、授乳スペース、夜間照明、防犯動線の整備を標準化します。地域の女性団体や当事者が計画・訓練の段階から関与することで、運用の実効性は高まります。
第三の柱は、ジェンダー平等と人材・働き方改革の一体推進です。女性管理職比率や意思決定層の多様性を各自治体・企業のKPIとして可視化し、登用・研修・評価の仕組みを改善します。STEM分野の学び直しやデジタル技能の取得支援を拡充し、就業ニーズに合った時間帯・場所で講座を提供します。保育・学童・介護といったケア基盤の整備、柔軟な働き方の制度化、性暴力・DVの予防と相談支援の強化を同時に進め、働き手の層を厚くし、地域の生産性を高めます。創業・成長期の女性起業家には、低利融資やエクイティ支援、公共調達での機会拡大を組み合わせ、地域の新陳代謝を促します。
第四の柱は、資金循環とデータ・ガバナンスの確立です。グリーンボンドやSDGs債を活用し、学校の省エネ改修、避難所の再エネ・蓄電整備、河川・道路の気候適応、食品ロス削減と地域フードセーフティ網など、気候・防災・福祉を束ねたポートフォリオに継続的に資金を振り向けます。成果指標(エネルギー、廃棄物、交通、防災、ジェンダー、福祉など)をダッシュボードで定期公開し、入札や補助の評価基準にKPI改善度を組み込むことで、政策と事業を結果志向へ転換します。性別・年齢・地域別の統計を整備し、エビデンスに基づく意思決定を徹底します。
以上の四本柱は互いに連動します。脱炭素投資は雇用と人材育成を促し、ジェンダー平等はイノベーションと地域活力を高め、強靱化は平時の省エネ運用と災害時の安全を支えます。資金とデータの設計を共通基盤としながら、県・市町村・企業・大学・NPO・市民が役割を分担することで、取り組みは持続力を得ます。世界全体が遅れる中でも、茨城は技術力と現場力を備えています。「脱炭素」「強靱化」「包摂」「ガバナンス」を四つの柱として据え、ジェンダーの視点を横断的に組み込むことが、2030年に向けた確実な前進につながります。どの地域でも、誰一人取り残さないことを前提に、足元の実装から着実に進めてまいります。